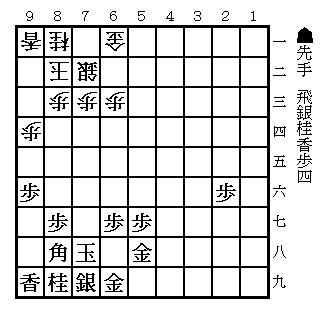
将棋のルールの中に、「同じ筋に、二枚の歩を打ってはならない」というものがあります。
これは、二歩の禁止と言って、たとえば、左図でいうと、2、5、6、8、9筋には、自分の歩がありますので、この筋に、持駒の歩を打ってはいけないのです。
したがって、歩が打てるのは、1筋、3筋、4筋、7筋ということになります。
この「二歩」というのは、反則の中で、最も良く出てくるものです。
歩を打つときは、二歩になっていないかどうか、よく確かめてから、打つようにしましょう。
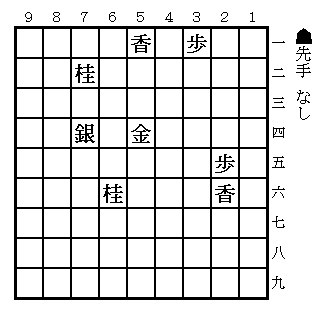
さて、二歩以外にも、打ってはいけない場所が、ほんの少し存在します。
それは、「動けない駒を作ってはいけない」というルールがあるからです。
今、左の図の、3一歩、5一香、7二桂は、動くことができません。したがって、この位置に、駒を打ってはいけないのです。
前に、香や歩は、一段目に動くときは、必ず成らなければならない、と言ったのも、この動くことのできない駒を作ってはいけない、というルールに基づくものだからです。
ただし、2六香や、6六桂のように、今は動くことができなくても、いずれ、2五の歩がどけば、動くことができる訳ですから、これは、動けない駒ではありません。
したがって、香、歩の一段目と桂の一段、二段目のみが、打つことができず、また、成らずで動くことができない、ということです。